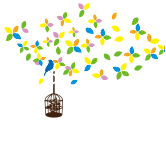【セミナー】『この歯はもう抜くしかないですか?』〜外科的歯内療法の最前線から学んだこと〜
2025.07.06
こんにちは。かいり歯科クリニックの院長の戸田です。
「この歯はもう抜くしかないですか?」
こんな相談を日々の診療の中で、患者様から悲しそうなお顔でされることがございます。
そんな『歯を残したいという患者様の想い』に少しでも応えたいという気持ちから
この度、当院の非常勤歯科医師 小笠皓平(おがさこうへい)先生が
これまで取り組んできたCTやマイクロスコープを活用した精密な根の治療(精密根管治療)の知識と技術をより一層深めるべく
「第29回 マイクロサージェリーアドバンスド実習コース」(講師:澤田則弘先生)
に参加してまいりました。
※澤田則弘(さわだ のりひろ)先生とは
日本を代表する歯内療法(根管治療)およびマイクロエンドの専門歯科医で、主に東京・四谷にある「澤田デンタルオフィス」を運営されています。また、若手歯科医向けに教育・講演活動にも注力されている先生です。
歯科医師 小笠皓平先生
小笠皓平先生は、国立徳島大学歯学部のご出身で、小・中・高・大学と一貫してバスケットボール部に所属してきた、身長180cmを超える体格の大きな先生です。
その堂々とした見た目とは裏腹に、性格はとても温厚で優しく、患者さまやスタッフにも常に丁寧に接してくださいます。
また、真面目で勉強熱心な一面もあり、日々研鑽を重ねながら、より良い医療を提供するために努力を惜しまない先生です。
そんな小笠先生が、マイクロスコープとCTを活用した外科的歯内療法(後述:歯根端手術)の最新知識と、治療に向き合う術者の姿勢について学んできたことをご紹介させて頂きます。
歯の根の中は目に見えない細菌の集落〜CTと高倍率視野で細菌と戦う〜
歯の根の治療(根管治療)の目的は、根の中の細菌を徹底的に取り除くことです。
しかし実際の診療では、X線(レントゲン)画像上では明確な原因が見えないにも関わらず、痛みや違和感が続くケースもあります。
その原因として、根の管の中の分岐(側枝)や 根の管と管の間のつながり(イスムス)、根の先端部(根尖部)などの複雑な形の中に隠れた細菌が考えられます。
こうした見つけづらく取り除きづらい細菌に対応するには、マイクロスコープや高倍率ルーペによる拡大視野と、CTによる三次元での診査・診断が必要となります。
根の治療は『基礎工事』〜精度が未来の歯の寿命を決める〜
根の治療は、単に痛みを取る処置ではありません。
その後の詰め物や被せ物がしっかりと噛めるようにするための
「土台づくり」=基礎工事
です。
治療には細かく時間のかかる作業が多く、根の中の細菌を完全に除去するには高い精度が必要です。
わずかな見落としや妥協が、再感染や再治療につながるリスクとなるからです。
セミナー講師の澤田先生は講義の中で
「患者様から託された歯には、決して妥協してはならない」
と繰り返し話されていたそうです。
この言葉はわれわれ歯科医師にとって、診査・診断から保存が出来ないと判断した歯に対して、改めて見直すきっかけとなるお言葉だと思います。
最終手段の歯根端手術〜高度な技術を日々のルーティン診療へ〜
今回のセミナー実習には歯根端手術の技術について細かい技術指導がメインとなっていました。
歯根端手術(Apicoectomy)とは
根管治療を行っても治らない、または再発してしまった病変に対して、歯の根の先端(根尖)を外科的に切除し、病巣を除去する治療法です。
【目的】
“ 根尖病変(歯根の先にできた膿や炎症)”に対して
・根管治療で治らない
・再発してしまった
・根管の形態が複雑で治療器具が届かない
などの場合に、
歯を抜かずに保存するための最終手段
として行います。
最終手段の歯根端手術は歯根の裏側に残るわずかな感染源をいかに可視化し、確実に除去するかといった、非常に高度かつ臨床的な技術の習得が必要となります。
また、技術以外でもマイクロスコープ下での操作での注意点や、CT画像の読影の仕方、診断へのアプローチの大切です。
歯をできる限り残す治療を
かいり歯科クリニックでは、マイクロスコープとCTを用いた精密な診査・診断のもと、
時間と手間を惜しまない精密根管治療・精密歯根端切除を自由診療で行っています。
小笠先生が学んだ内容をクリニック内でも落とし込み、
今後も1本でも多くの歯を残すために、患者様と誠実に向き合ってまいります。
歯でお困りの方はお気軽にご相談下さい。


![]()

![]()